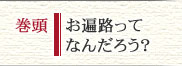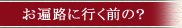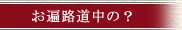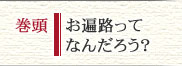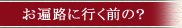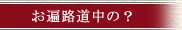江戸時代を境に全国で民衆の巡礼が盛んになってゆきました。当時、四国での巡礼者の特徴として挙げられるのが「職業遍路」の多さがあります。日本の難民と呼ばれた職業遍路はどのような人々だったのでしょうか?
「職業遍路」とは一時的な遍路ではなく、四国を巡りつづけることを職とした人々のことです。ではなぜ、かれらは四国を巡りつづけるに至ったのか、そして、どのようにして生計を立てていたのか。そこには様々な理由で地域や社会からはじきだされた人々が遍路となり、「お接待」と呼ばれる風習によりかろうじて生き延びていた姿が見えてきます。
「お接待」とは遍路に対して支援する昔ながらの風習です。無償で宿を提供にしたり、食べ物などを支援します。険しい道のりだった四国遍路において、お接待は遍路の存続を大きく支えました。現在でも四国に残るお接待は遍路の歴史に大きな影響を与えることになります。なかでも、職業遍路が四国に流入したことはこの接待を抜きには考えられません。
 |
四国偏路獨案内(しこくへんろ ひとりあんない) 江戸時代のお接待する人々とお遍路たち。
|
職業遍路で代表的なものが病気によって故郷を出た人々です。中でもよく知られたのが、ハンセン病患者の遍路で、当時、ハンセン病は遺伝性(※
注1)と考えられていたため家族に病人がでると、人に知られる前に遍路に出しました。(※
注1:ハンセン病は遺伝病ではなく、現在、完治する病気です。又、元患者の方から感染もしません。ハンセン病に関して詳しくは →「モグネット」のページへ)その他にも重病の病人や身体障害者などが遍路となり四国を巡りつづけました。彼らは「病気遍路」や「へんど」などと呼ばれ、時には一般の遍路と差別されることもありました。彼らは一般的な遍路道を避け、遍路屋に泊まることも出来ず、野宿や本堂の軒などで一夜を過ごすなどして、一般の遍路とは離れ四国を巡りつづけました。
 |
<母娘遍路像>
善通寺に建立後ハンセン病資料館へ移転。
ハンセン病となった人々が遍路として四国を巡っていたことを今に伝える。
|
その他の職業遍路の主な人々は貧困による難民層です。身分制度の中で低階級の労働者の生活は厳しく、貧富の差は広まる一方でした。失業者には何の保証もなく、路頭に迷った多くの人々が接待をあてに遍路になりました。1781年、富後日出(大分)布令の中で失業者が増え多くの人々が四国遍路に流れたことが書かれています。また、飢饉が起こるたびに多くの人々が四国に流れました。天保の飢饉の際、加太浦(和歌山市加太)の船着場には四国へ渡るための極貧者があふれ、そういう人々を無料で乗船せたとが記されています。
故郷を追われて遍路になった人々は札所を一周しても帰る所もなく、結局は接待を当てに死ぬまで四国を歩きつづけなければならなず。こういった人々の中には、まったく巡礼はせずただ接待を当てに四国を巡る者や、賊化して空巣や強盗をはたらく者たちも現れるようになります。このような遍路は「偽遍路」や「乞食遍路」などと呼ばれ、こういった事態に藩では遍路の規制に乗り出すことになります。
藩では法令を出し、職業遍路による犯罪や風紀へ対策を打ち出します。遍路には往来手形を提示させ、滞在期間にも期限を設けた。また、規定の遍路道を外れて歩くことも禁止しするなど、再三にわたり遍路の規制法令を出しました。
しかし、明治に入っても職業遍路は減ることなく、規制はより厳しいものとなってゆきました。明治政府が神道を推奨したことも相まって、遍路狩りが行われるようになると一般の遍路までが捕らえられることもありました。気候の温暖であった土佐(高知)はもっとも乞食遍路が多く、きびしい規制・弾圧が行われました。このような流れから土佐藩では”遍路自体を拒絶すべし”との論議も生まれ、土佐を中心に遍路を冷遇する空気ができていました。
明治から大正にかけて遍路は減少期をむかえます。遍路の規制に加え、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく;仏教を廃し神道に拠らんとする思想運動)や戦争に向かう時代の中で一般遍路の数は減少していきました。1918年から九州日日新聞にて連載された高群逸枝による「娘巡礼記」の中で、当時の四国遍路は巡礼者というより貧困者や病人の難民といった印象を伺えます。このころの遍路は貧しい人の最後の行き所といった印象も強く、善根宿には職業遍路が溢れてたとあります。
病気や障害、貧困のほかに罪や偏見などによって故郷を追われた人々なども遍路となりました。彼らは社会福祉制度が確立される昭和40年代までその数を減らすことはなく、四国遍路は福祉が発達するまでの行き場を失った人々の受け皿ともなりました。結果としてお接待は彼らの生計を支えることにもなっていきました。四国には故郷に帰ることなく、人知れず果てた無縁仏の遍路墓が今も無数に残っています。
 |
<無縁仏の遍路墓>
四国のへんろ道には今も多くの無縁仏の遍路墓が残っています。
|